本ページはプロモーションが含まれています
【結論】9/1「防災の日」は“点検&共有”に全振り。30分だけでもOK
毎年9月1日は防災の日。この日を含む8/30〜9/5は「防災週間」です。由来は1923年9月1日の関東大震災で、台風シーズンの節目という意味もあります。まずは「備蓄・家族連絡・避難情報」の3本柱を今日アップデートしましょう。
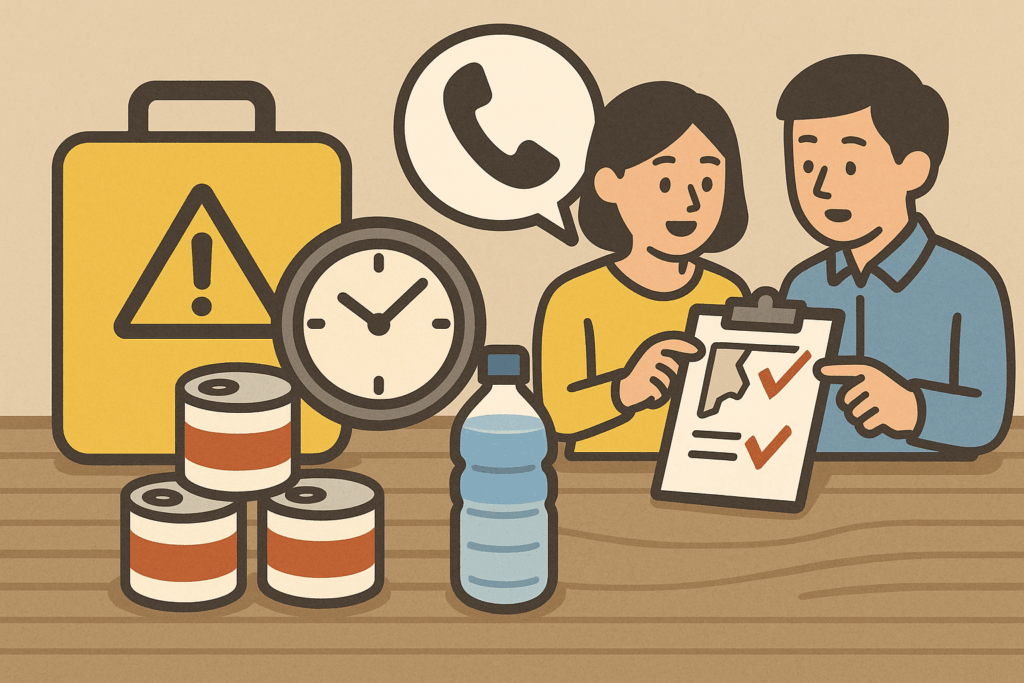
防災の日って何?(超要約)
- 毎年9月1日=防災の日。9/1を含む1週間が防災週間。全国で講演・訓練などを実施。
- 関東大震災(1923/9/1)を教訓に制定。
まず“今日”やること:タイムボックスで一気に終わらせる
A. 15分ショート(最低限)
- 5分|ハザード確認:自宅・職場・学校をハザードマップポータルで検索(浸水・土砂・津波)。最寄りの高台/避難場所を1つメモ。
- 5分|スマホ設定:緊急地震速報とJアラートが鳴る設定になっているか確認。家族の端末もチェック。
- 5分|家族連絡ルール:集合場所(第1/第2)と安否確認手段(電話/メッセージ/災害用伝言板)をLINEノート等に固定。
B. 60分しっかり(できれば今日)
- 備蓄棚の棚卸し(20分):水は1人1日3L×3日分以上を目安。主食(アルファ米/レトルト)、おやつ、乳幼児/高齢者用も確認。賞味期限をメモ。
- 非常持出袋の再パッキング(15分):ライト・モバイルバッテリー・常備薬・現金・マスク・簡易トイレ・充電ケーブル。
- 家具固定チェック(15分):寝室とキッチン優先。L字金具/突っ張り/滑り止め、ガラス飛散対策。
- 避難動線の確認(10分):自宅→一時集合→広域避難の徒歩ルートを地図に書き込み。
チェックリスト
- 水:3L/人/日 × 最低3日分(可能なら7日)
- 主食:アルファ米・パックご飯・麺類/副食:缶詰・栄養補助食
- 電源:モバイルバッテリー、乾電池、ソーラーや手回し
- 灯り:ヘッドライト(両手が空くタイプ推奨)・ランタン
- 衛生:簡易トイレ・ウェットティッシュ・ポリ袋・衛生用品
- 医療:常備薬・絆創膏・処方薬の情報
- 情報:携帯ラジオ/複数アプリ+ブラウザで災害情報
- 書類:身分証・保険証・保険契約・連絡先の紙控え
- 衣類:防寒・雨具・替え下着/スニーカー
- ペット用品:フード・水・ケージ・マナー袋
スマホで受け取る公式情報の基礎
- 緊急地震速報(気象庁):強い揺れの到達を素早く知らせる仕組み。対応動作を家族で練習。
- Jアラート(消防庁):自治体の防災無線等が自動起動。避難に直結する情報は必ず受信できるように。
- ハザードマップ:国のポータルで自宅・職場のリスクを地図で重ね合わせ。スクショを家族に共有。
家の安全アップデート(転倒・出火・停電対策)
- 寝室の安全化:背の高い家具は固定、枕元上の棚は避ける。ガラス飛散対策フィルム。
- キッチンの火元:地震時自動消火・感震ブレーカーの導入検討。
- 通路の確保:玄関と廊下は段ボール置き場にしない。避難の“動線”を空ける。
- 固定の具体(内閣府ガイド):ビス長30mm以上、太さ4mmなど基本を守る。
2025年の注目ポイント
- 公式テーマ期間:2025年も8/30〜9/5が「防災週間」。各自治体・企業の訓練や啓発イベントが集中します。
- 関連日:8/26「火山防災の日」。火山地域の方は避難ルートや降灰対策も見直しを。
公式リソース(保存推奨)
- 内閣府「防災の日/防災週間」:趣旨・期間・取組
- ハザードマップポータル(国土地理院/国交省)
- 緊急地震速報の基礎(気象庁)
- Jアラートの仕組み(消防庁)
- (参考)東京都「東京防災」デジタル版・PDF版
まとめ
防災の日は“意識する日”ではなく“更新して共有する日”。ハザードの可視化・スマホの受信設定・備蓄の棚卸し・家族ルール共有・家具固定を、今日のうちにひとつでも前進させましょう。明日以降の行動が軽くなります。



コメント